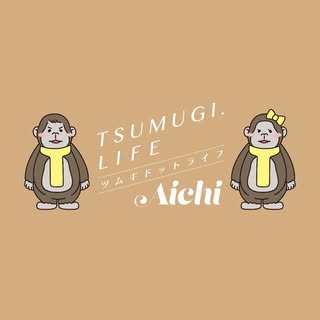時代を旅する雑誌専門図書館「よみかけ文庫」を訪ねてみた。

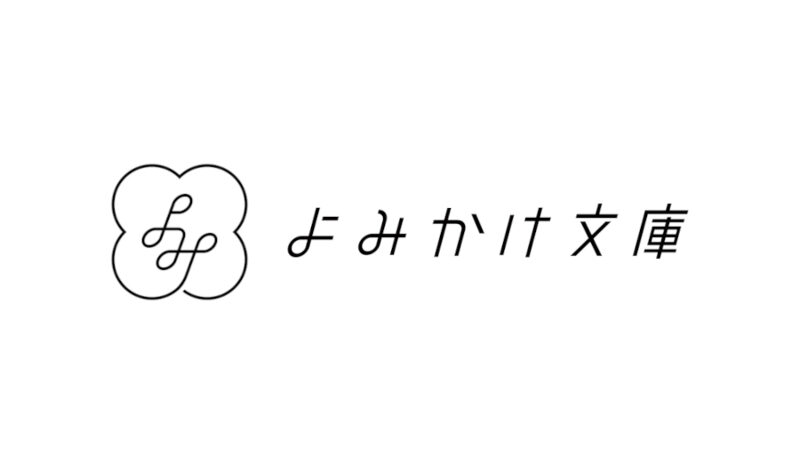
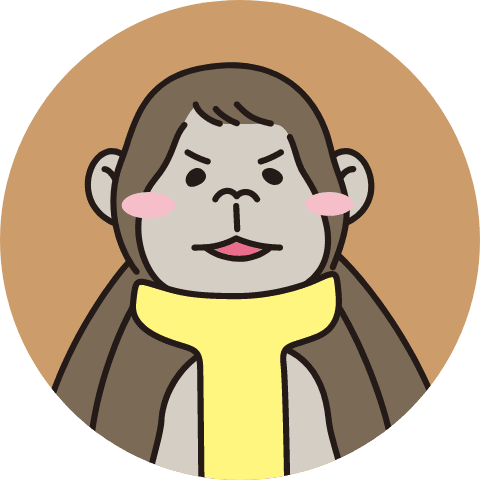
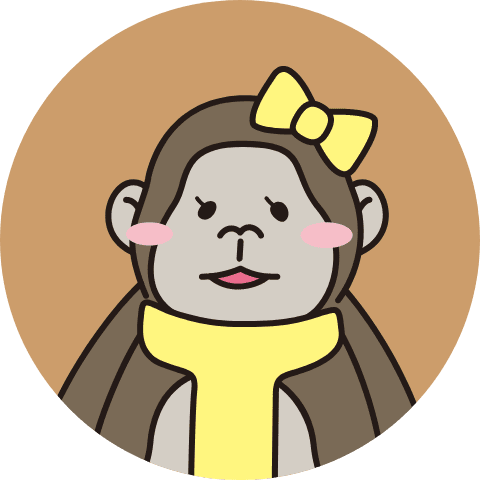
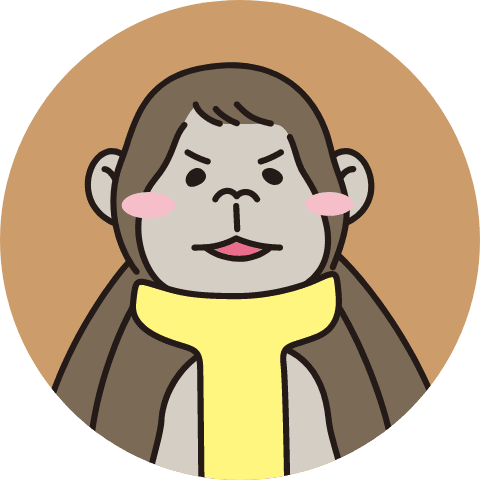
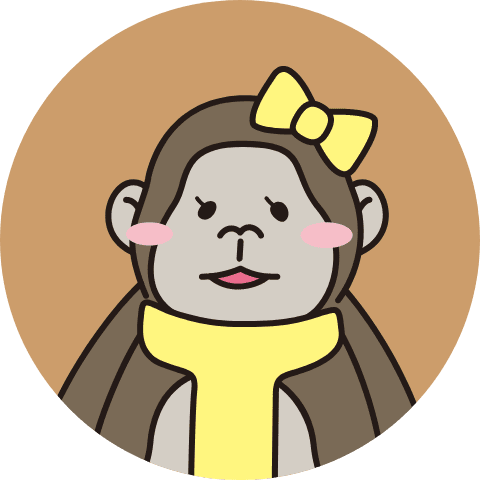
昭和末期から・平成・令和にわたる膨大な雑誌コレクションを自由に閲覧でき、時代を超えた文化の旅を楽しむことができる。今回は館主のワタナベさんに、この特別な空間を生み出したきっかけや想いについて伺った。
- 雑誌愛から生まれた「読みかけ」の哲学
- サードプレイスとしての価値を重視
- 昭和から令和まで、時代を横断するコレクション
- 3階は多目的スペース「culturalspace 生存」
- 持続可能な運営への想い
①雑誌愛から生まれた「読みかけ」の哲学
「よみかけ文庫」はカルチャーマガジン専門の図書館だ。は2021年8月に一宮市の木曽川町でオープンし、2025年6月28日に現在の本町へ移転した。映画、音楽、アート、デザイン、ゲーム、ファッションなど多岐に渡るカテゴリの雑誌が網羅されている。カルチャーマガジンを愛する人々のための特別な場所として、訪れる人々に知的な刺激と発見を提供している。
「雑誌専門の図書館は、ほとんどありません。大宅壮一文庫図書館とうちくらいかもしれませんね。大宅壮一文庫は「ありとあらゆる雑誌を取り揃えてるのに対し、うちは自分の守備範囲の雑誌しかありませんが、それでも幅広く揃えているため、訪れた方は何かしら引っかかる部分があるはずです。」
「よみかけ文庫」というユニークな名前の由来を聞くと、ワタナベさんは少し自虐的に笑いながら答えてくれた。
「雑誌って『積読』という概念があまりないじゃないですか。本と違い、必ずしも最初から最後まで読み切る必要がありません。読了の概念がないので、プレッシャーや呪縛がない。そんな気軽さを表現しました。あえてひらがなで柔らかい感じで表現することで、取っつきやすさも出せていると思います。」
この哲学は、図書館の運営方針にも反映されている。利用者は時間を気にせず、気になるページだけを眺めても良いし、深く読み込んでも良い。そんな自由な読書体験を提供しているのだ。
「ここにはいろいろな雑誌があります。すごく素晴らしい記事がたくさんあるんです。眠っている記事もたくさんあります。本来ならば全部読んで自分に取り込みたいとは思うのですが、全て読み切れていないのが現状です。僕が死ぬまで絶対読み終わらない。一生かかっても読み切れないという意味も込めた「よみかけ文庫」なんです。」
完璧を求めがちな現代において、「読みかけでいい」という考え方は、きっと訪れる人の心を楽にしてくれるだろう。

②サードプレイスとしての価値を重視
「ここに並んでいる雑誌の9割以上は自分の所有物なんです。」そう語るワタナベさん。
図書館を開設したきっかけは、2021年のコロナ禍にさかのぼる。当時、私設図書館や独立系書店がブームになっていたこと、自身の膨大な雑誌コレクションの処分に悩んでいたことが重なった。
「本来なら処分するか売ってしまうのが普通だと思うのですが、もったいなくてできませんでした。貸しコンテナに仕舞っておこうかとも思ったのですが、コンテナを借りるのもお金はかかってしまいますし、本当に読みかけのまま一生開封しないだろうなと思ったらもったいないと感じたんです。」
コレクションは普通に今でも販売されているものから、値段もつかないようなものまで幅広く含まれる。ワタナベさんが考えたのが「たくさんの人に触れてもらうこと」だったのだ。
個人が運営している一般的な私設図書館は、自宅の一室を提供しているものが多い。しかしワタナベさんはクオリティを高めたいと、あえて店舗を借りて「よみかけ文庫」を営んでいる。
「前から漠然とお店をやりたいとずっと思っていたんです。服屋でも雑貨屋でも何でもよかった。でも図書館をつくったことで、自分はお店で商売をしたいんじゃなくて、単純にサードプレイス(第三の場所)が欲しかったんだなって気づいたんです。」
現在の「よみかけ文庫」は、まさにワタナベさんが理想とするサードプレイスとして機能している。家でも職場でもない、心地よい第三の居場所として多くの人に愛されているのだ。


③昭和から令和まで、時代を横断するコレクション
「よみかけ文庫」の最大の特徴は、時代を横断した雑誌コレクションにある。40代後半のワタナベさんは、昭和・平成・令和の時代を歩んできた。雑誌のコレクションも、それぞれの時代をある程度網羅したものとなっている。
興味深いのは、若い世代の来館者が多いことだ。デザイナーやクリエイターが資料として活用することも多く、20年以上前のデザイン雑誌でも現在の感覚で見ると斬新に映るそうだ。
「1990年代の雑誌でも、意外と色褪せていないんですよ。その時代の流行やスタイルが載っているし、広告を見るとその時代の文化が一目でわかる。時代を飛び越えて楽しめる資料として価値があると思います。」
雑誌は時代の記録でもある。たとえば1997年には「新世紀エヴァンゲリオン」の劇場版と「もののけ姫」の公開が重なった「アニメ当たり年」だった。歴史を振り返る楽しさも雑誌の魅力であり、それを堪能できるのがよみかけ文庫の醍醐味なのだ。


④3階は多目的スペース「culturalspace 生存」
現在の「よみかけ文庫」は、2階と3階で異なる機能を持つユニークな構造になっている。
2階が「よみかけ文庫」として雑誌図書館の機能を担い、3階は「culturalspace 生存」という名前の多目的イベントスペースとして活用されているのだ。
3階のスペースは、ワタナベさんが自ら設計事務所と協力して作り上げた空間だ。天井を取り払い、螺旋階段を設置するなど、大胆な改装を施している。

「3面映像のプロジェクションマッピングもできるし、音楽イベントも可能です。ギャラリーとしても、撮影スタジオとしても使える多目的な空間になっています。本格的なDJブースも設置されており、トークイベント、音楽イベント、モデルさんの撮影会など、さまざまな用途で活用できます。たいていの表現がここでできますね。」

6月28日に行われたオープニングパーティーが開かれた。このイベントには、DJのKAZUYA さんTAMANEGIさんQPQ さんやM.Y.Aの演奏が行われ、盛大な盛り上がりをみせたと話してくれた。
このスペースは若いアーティストや作家にできるだけ安価で提供したいという想いがある。映像も音楽も大半の表現活動ができる環境を整え、創作活動の入り口として機能させたいと考えているそうだ。


⑤持続可能な運営への想い
「よみかけ文庫」のユニークな点は、収益を追求しない運営方針にある。入館料制を取っているが、これは「持続可能にするための資金」という位置づけだ。
「このお店は完全に自己満足の極地です。そもそもバランスなんて取れていない状態でスタートしているので、そこに商売のエッセンスを入れてバランスを取ろうとすると、逆に崩壊してしまうと思ったんです。」
ワタナベさんはバンド活動をされていたが当時は自己資金でライブやCD制作を行い、チケットやCD売上があっても出費の方が大きい状況だった。それと同じ感覚で図書館運営を続けているという。
「儲けを考えた途端に、自分が求めているものと違うものになってしまうと思っているんです。商売じゃないのになぜこのクオリティなのかというアンバランスさが心地いいんです。」
よみかけ文庫や「culturalspace 生存」について語るワタナベさんは、心底楽しそうだ。
「ここの運営は単純に楽しいですね。ただ、本業では馬車馬のように働いてますよ。本末転倒なんですけどね。本当はこの手のカルチャーにずっと浸っていたいんですが、時間が無さすぎて、本は読めないしは映画は見れない。音楽も聴けない、そういうジレンマはありますね。」
それでも続ける理由として、ワタナベさんは、自分が若い時にそういう、儲けを度外視してカルチャーに触れさせてくれた場所を提供してくれた先人たちがいたからこそ今があると振り返る。気がついたら自分が「提供する側」になっていた。その想いがワタナベさんの原動力なのだろう。
座右の銘を取材の場で尋ねたところ、「人は寝るために起きている」と答えたワタナベさん。この言葉には深い意味があるわけではなく、とっさに出た言葉だというが、どこか彼の人柄と「よみかけ文庫」の雰囲気を表している気がした。
収益を度外視してカルチャーな価値を大切にする「よみかけ文庫」。雑誌を通じて時代を旅し、新しい発見や懐かしい記憶に出会える特別な空間として、これからも多くの人に愛され続けることだろう。読みかけでも大丈夫、そんな心地よい空間を、ぜひ一度訪れてみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら

 一宮市
一宮市