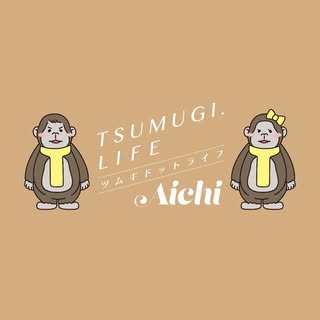「できない」を「やってみる」に変える場所「古民家飲食店ぶち」を訪ねてみた。


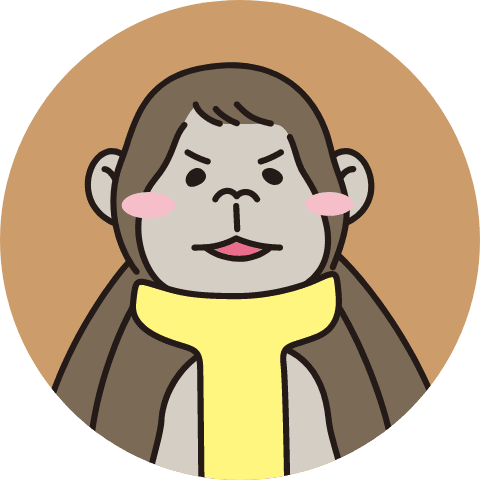
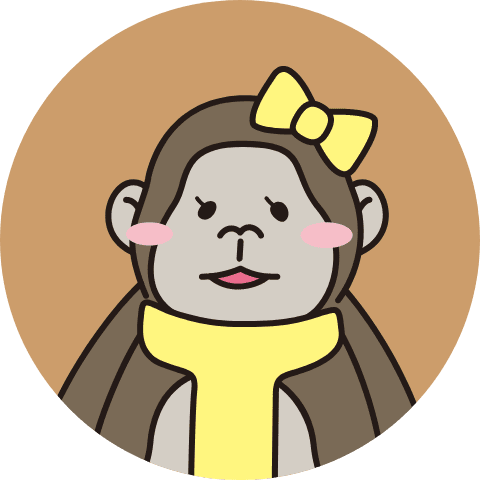
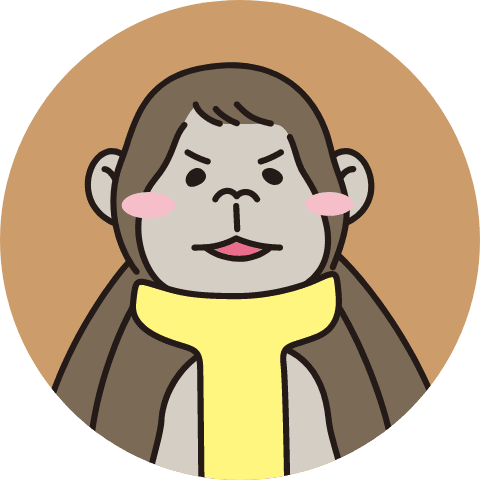
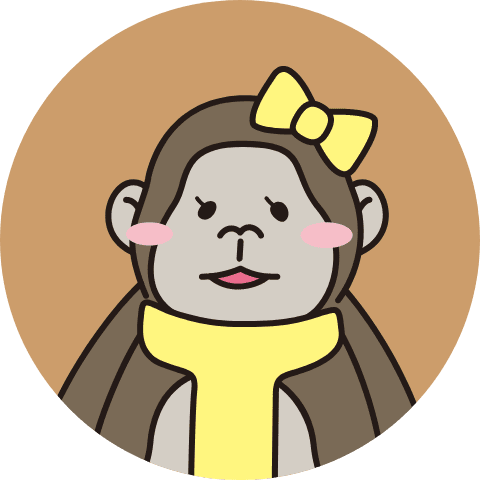
一見すると普通の飲食店だが、地域の子どもたちが自由に過ごしたり、ふらっと旅人や芸人さんが泊まりに来たりと、「みんなが集う場所」として多くの人に愛されている。今回は店主の英二(えいじ)さんに、お店を始めたきっかけや大切にしていることについて伺った。
- 出会いの縁を大切に繋げていく場所
- 「できない」と決めつけずにまずやってみる
- 地域の子どもたちの駆け込み寺
- 宿泊もOK、飲食店の枠を飛び越えた活動
- つながりを大切に、誰かの夢をサポートしたい
①出会いの縁を大切に繋げていく場所
2023年3月21日にオープンした「古民家飲食店ぶち」。名鉄二ツ杁駅から徒歩約10分のところにある、築数十年の日本家屋をリノベーションした、隠れ家のようなお店だ。「中と外を繋ぐ『縁』側のような存在」というコンセプトの通り、お店では多彩なイベントが催され、お客様同士が自然と交流している。
「古民家飲食店ぶち」は、どこか懐かしい雰囲気の中で食事を楽しめるお店だ。目玉となるのは糀を使った唐揚げ。国産の生鶏を使用しており、糀の甘みを感じられるふっくらジューシーな一品だ。「ぶち」には、塩糀、醤油糀、玉ねぎ糀、ニンニク糀など数種類の糀が常備されており、これらを調合してさまざまな料理を生み出している。
店名の「ぶち」にはどのような意味が込められているのだろうか。
「みんなが集まれる『縁』のイメージから、『えん』と言う案もありましたが、子どもたちも呼びやすい『ぶち』と言う響きにしたんですよ。」
店のロゴは五角形の中に「ぶ」の文字が書かれ、当時音楽好きな人が周りに多かったため、音楽を通じて仲間が集まる場所という意味で「ぶ」の濁点が音符になっている。五角形は家に見立てられ、「家(うち)のような居場所にしたい」という想いが込められている。「ぶち」では「音ぶち」と呼ばれる音楽イベントを定期的に開催しており、気軽に音楽に触れられるのも魅力だ。


②「できない」と決めつけずにまずやってみる
英二さんは、最初から飲食店をやろうと思っていたわけではなかったという。
「もともと、友だちがシェアハウスを2つ運営していました。その2つのシェアハウスの住人同士が気軽に集える場所を作ろうという話になったんです。でも、ぶちの前を高校生たちが通りかかって『ここ何?』と興味を持ってくれて、コロッケだけでも食べていくようになり、徐々に近所のおじいちゃんおばあちゃんも来るようになって、気づいたら飲食店っぽくなっていましたね。その後、ご近所さんが空き物件を紹介してくれて、3つ目のシェアハウスが出来たんですよ。」
そんな英二さんは古民家飲食店ぶちを始める前、保育士や演歌歌手、実家の鰻屋やキッチンカーなど様々な仕事を経験して来た。愛知万博のスタッフとして働いたこともあるという。特に保育の現場での経験は、英二さんの現在の活動に大きく影響している。
英二さんが勤務していた保育園では、重度の障がいを持つ子どもを受け入れたことがあった。医者からも長く生きられないと言われていたが、英二さんたちは毎日一緒に体操をし、愛情を込めてケアをした。その結果、当初宣告されていた年齢を超えて、その園に通い続けることができたのだそうだ。
この経験から英二さんは、「みんながやれないと決めつけていることでも、やろうと思えばやれることが意外にある」と気づいたという。この哲学は現在の「ぶち」の運営にも反映されている。
「この場所で古民家カフェをやろうとした時も、友人たちからは『無理だ』と言われました。でも、それは彼らの経験上の話であって、やってみなければわからない、と信じてお店を開きました。実際にやってみたら、地域の方々の協力もあって、今もこうして続けられています。」
英二さんの「まずやってみる」精神が、既存の常識にとらわれない居場所づくりを可能にしているのだ。


③地域の子どもたちの駆け込み寺
「古民家飲食店ぶち」の最大の特徴は、食事を提供する場所であると同時に、地域の人々、特に子どもたちの居場所になっていることだ。子どもたちが学校帰りに寄って勉強したり、ゲームをしたり、時には横になって休んだりする姿も珍しくない。
「前に、学校やフリースクールにも行けていないという中学生の子が、お母さんとここに来て『ここなら来れそう』って言ってくれたんです。それからよく通ってくれるようになって嬉しかったですね。他にも、ここで絵を描く女の子もいます。お客様と会話することで、彼らの世界が、外とつながり広がっていっているのを感じます。」
居場所を探す子どもたちを、温かく迎え入れる英二さん。その取り組みを聞きつけたメディアから取材の申し込みが多かったが、長らく断ってきたという。
「取材を受けると、いいところだけが切り取られて報道されがちです。そうすると、その報道でここを知った人たちが、すごい場所なんだと期待を持ってやってくる。でも、この子たちはゴロンと横になっているときもある。報道と実際の姿のギャップで、子どもたちが居づらくなることは避けたかったんです。」
飲食店という枠組みを超えたぶちの活動は、地域からも評価されている。近隣の高校では、メニュー開発から店舗運営までをぶちで体験する授業を行なっており、もう7年も続いているという。
「高校生たちが自分たちで考えた料理を作って提供するんです。私は店を貸すだけで、彼らの自主性に任せています。こうした方がいいよとアドバイスはしません。ただ『料理がわからない、どうしたらいい?』と切羽詰まった時だけ、ヒントを出します。先生ともすっかり仲良くなって、今ではすべて任せてくれています。」
学生に「これができる、できない」と言うのではなく、失敗も含めて自分で考え、行動する機会を提供する。自ら考え、創造する場を若者に提供することで、彼らの成長を後押ししている。意欲を持つ若者を応援することが、英二さんの喜びとなっているのだ。この活動は周辺地域にも広まり、「うちも、ぶちさんのような高校生食堂をしてみたい」というお店も出てきているそうだ。


④宿泊もOK、飲食店の枠を飛び越えた活動
「ぶち」には、世代を超えた多様な人たちが訪れる。
「この間も1歳くらいの赤ちゃんを連れたお母さんたちが6組くらい来ました。子どもたちを遊ばせておいて、お母さんたちはゆっくり食べたりもできるんです。」
子どもの声が気になるお客様には「この声がうるさいと感じて耐えかねる場合は、退店していただいても構いません」と伝えている。
「子どもは動けないけど、大人で嫌だなと感じる人は、逃げればいいだけだからね。」
と、子どもを優先する姿勢が印象的だ。ひと組だけのために貸し切るというのもOKにしているそう。いろいろな事情を抱える人にも寄り添い、拠り所となっている「ぶち」。何と時には、地域の子どもたちのお泊まり会で使用したり、高校生のグループが合宿場所として利用することもあるそうだ。
「1階だけでなく2階にも部屋があるのでそこも貸し出して、時にはどうぞと開放する事もあります。高校の陸上部の子たちが『学校は合宿のお金が出ないから、ここで合宿したい』と言って、10人ぐらいが寝袋持参で泊まっていきました。その後、県大会に行きました!って報告をくれたんですよ。」
英二さんは、子どもの宿泊に対して基本的に費用を取らない。「お金をもらってしまうと、本当に来てほしい人たちが来なくなる」と考えているからだ。経営的には難しい選択だが、英二さんにとって大切なのは「人が集まる場所」という本来の目的を実現することなのだ。
「ぶちに、中学生の男の子が1人で遊びに来ることがあります。話を聞くと、家庭の事情があって、家に居づらいのかな、と感じています。でも、もし僕がお金を請求したら、彼は来れなくなってしまうんです。そういった状況になるのは望んでいません。」
ただし、大人に対しては区別して対応するという。
「大人が『俺もタダで泊まるわー』と言ってきたら『あなたは違うよ』と言いますね。そこはきちんと線引きしています。」
どんな人でも受け入れる、懐の大きな「ぶち」。しかし何でもOKというわけではない。その人が置かれた状況に応じて、臨機応変に判断し、対応しているというわけだ。

⑤つながりを大切に、誰かの夢をサポートしたい
英二さんは子どもの頃「夢を語る大人が大嫌いだった」と言う。明確な夢を持たない人もいる中で、「夢を持て」と押し付けることへの違和感があったからだ。そんな英二さんが今大切にしているのは、誰かの夢や挑戦を後押しすることだという。根底にあるのは、保育士時代の「やってみなければわからない」という信念だ。
「夢って言っちゃうと、破れてしまったときのダメージが大きい。それよりもまずやってみることが大事。誰かのやりたいことを実現させるのが、僕の新しい夢になっています。」
お店を訪れる人の中には、何かに挑戦したいけれど一歩を踏み出せない人もいる。そんな時、英二さんは背中を押す。
「ここには、パティシエになりたい高校生や、スイーツのお店を開きたい人など、夢を持つ人がたくさん訪れます。でも、完璧を目指そうとして動き出せないでいる。そういう人たちを応援したいんです。過去に間借りやレンタルキッチンで、やりたい!をやってみた人たちで、実際にお店を開いた人たちや今後お店を始める人は7組くらいいます。」
英二さんのサポートを受け、実際に海外で活躍するようになった人もいるという。
「ぶちに泊まりにくる芸人の子がいるのですが、ある日『ニューヨークで挑戦してみたい』と言い出したんです。その結果、今では海外の仕事もたくさん入るようになりました。フィリピンやインドに呼ばれたりもしているんですよ。今でも、日本に帰ってくると必ず立ち寄ってくれます。」
こうした成功例を聞くと、英二さんの場所づくりが単なる飲食店の枠を超えて、多くの人の人生を変える可能性を持っていることがわかる。事業を経営するにあたって、売り上げの問題は避けて通れない。しかし英二さんは、「縁」がお金よりも大切なものだと信じ、それを自らの生き方の軸としている。
最後に、英二さんの座右の銘を尋ねると、少し照れながらも「縁」という言葉が出てきた。
「『縁』という響きはちょっと照れくさいんですけど、今までの縁があって今があります。その人がこの世にいなくなった後も、つながっていくような縁をつくっていきたいですね。」
実は「ぶち」のもう一つの看板メニューであるソフトクリームにも、縁を感じるエピソードが詰まっている。実は英二さんは全国のソフトクリームを食べ歩くほど、大のソフトクリーム好き。しかしソフトクリームをつくる機械を導入するには多額の費用がかかるという問題があった。何とかアイスクリームを提供したいと募金箱を設置したところ、わずか1週間でいっぱいになったそうだ。
しかも、機械は地元の乳業会社の厚意により無料で貸与してもらえることになった。さらに電気工事も、ぶちでご飯を食べている地元の業者が買って出てくれることに。募金で得られたお金を使い、英二さんは感謝の気持ちを込めて、地元の人たちに無償でソフトクリームをふるまったそうだ。多くの人の縁で生み出された本格的なソフトクリームは、今も地域の人を笑顔にしている。

「古民家飲食店ぶち」は、単なる飲食店ではない、さまざまな縁が交差し、訪れる人の可能性を広げる空間だ。最新の営業日に関しては、古民家飲食店ぶちのインスタグラムにてチェックできる。ぜひ、一度、英二さんの温かな人柄に触れてみてほしい。

詳しい情報はこちら

 清須市
清須市