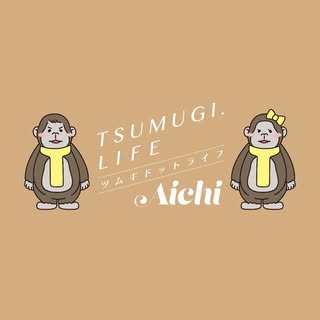伝統と独自性が調和する「茶房あずまや」を訪ねてみた。


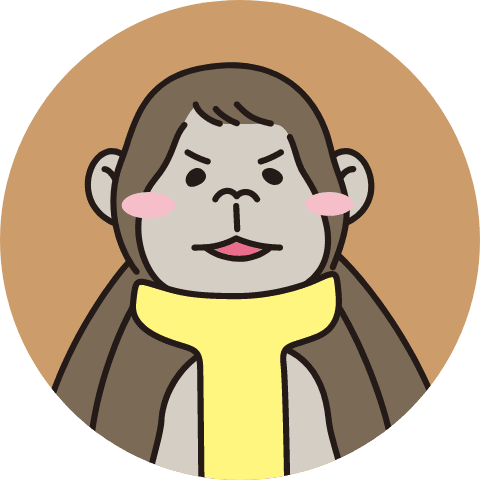
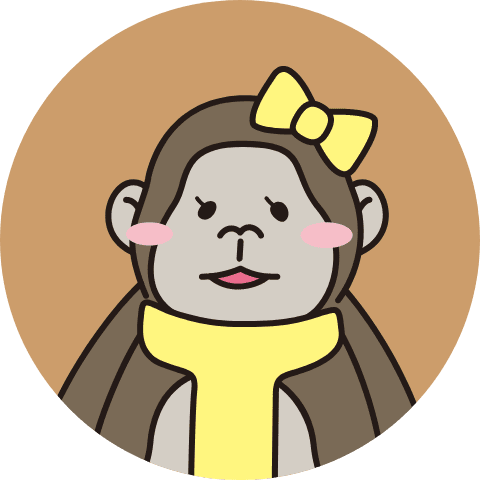
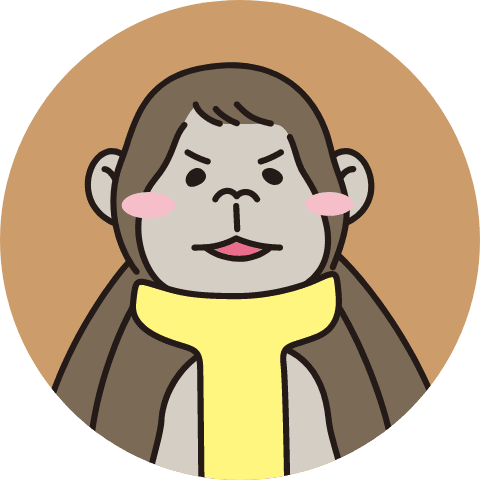
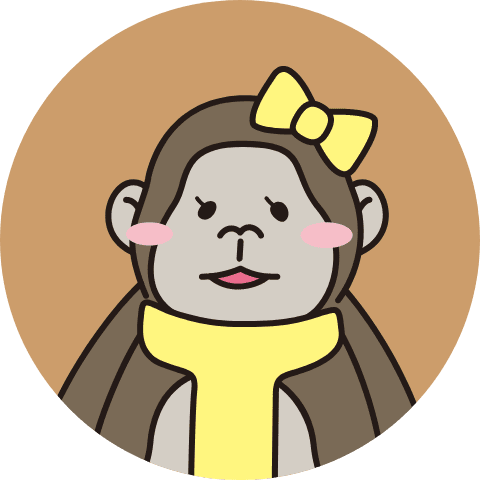
国際コーヒー鑑定士の資格を存分に活かした、こだわり抜いた極上の一杯が楽しめるお店だ。今回は、代表を務める松本 安弘(まつもと やすひろ)さんにお話をうかがった。
- 独自スタイルの構築
- 国際コーヒー鑑定士が届ける特別な一杯
- 一宮市に「美味しいコーヒー文化」を
- “101” に込められた思いと、コーヒーを通じた社会貢献
①独自スタイルの構築
喧騒から離れた静かな立地と、趣のある建物が特徴の隠れ家カフェ「茶房あずまや」。木の温もりが溢れるインテリアとレトロな装飾品で彩られた店内は、訪れる人々をどこか懐かしい気持ちにさせてくれる。
コーヒーや紅茶を提供する店、いわゆる喫茶店を表す「茶房」と、庭や公園などに設けられた休憩用の小さな建物を表す「あずまや」を組み合わせた店名には、「地域の人々がコーヒーを飲みながらくつろげる場所にしたい」という想いが込められているそう。
一杯ずつサイフォンで抽出するコーヒーは、味わい深さと贅沢さを存分に楽しむことができ、老若男女を問わず幅広い層に親しまれている。
幼少期から喫茶店を営む父の姿を見て育った松本さんだが、当初は飲食業に携わる考えはなかったのだとか。長らく従事した営業職を離れ、お父様のお店を手伝ううちに「地域でNo.1のコーヒーを提供したい」と強く感じるようになり、お父様が始めた場所で自分でお店をやっていく事を決意した。
「自家焙煎を謳うカフェや喫茶店を中心に、モーニングの提供がある店舗にはほぼ全てに足を運びましたね。リサーチを重ねる中で、『当店だからこそできる強み』を模索していきました。」
不安を抱えつつも、負けず嫌いな性格を活かし、周辺のカフェや喫茶店の調査を徹底的に行い、現在のスタイルを築き上げたという松本さん。
流行りを追うのではなく、コーヒー豆が持つ個性と甘みを最大限に引き出す焙煎を。量を重視する一般的なモーニングスタイルではなく、自家製あんこを使用したシンプルながらも質の高いトーストを。そして、蝶ネクタイを着用するフォーマルスタイルも、他店とは一線を画す独自性を演出している。


②国際コーヒー鑑定士が届ける特別な一杯
松本さんは、国内で約400人(2025年3月現在)しか保有していないとされる、世界で唯一の国際的なコーヒー鑑定の資格『Q Arabica Grader(Qアラビカグレーダー)』の持ち主だ。
正式名称は「Licensed Q Grader」で、主にコーヒーの官能評価やカッピング(テイスティング)を通じて、コーヒー豆の品質を科学的かつ客観的に判断する。この資格を持つことで、スペシャルティコーヒーの認定や取引において信頼性を高めることができるのだという。
「茶房あずまや」では、SCA(Specialty Coffee Association:スペシャルティコーヒー協会)が定める品質基準と、独自の基準をクリアした最高品質のコーヒー豆のみを買い付け、焙煎前後にハンドピッキングを行い“欠点豆”を除去することで品質ムラを防ぐという徹底ぶりだ。また、注文を受けてから最適な焙煎度合いで仕上げることで、鮮度を保ち、コーヒー豆本来の香りと味わいを最大限に引き出した“最高の一杯”を提供できる。
「コーヒー豆自体の品質と鮮度が高くなければ、どんなに丁寧に焙煎してもコーヒー豆本来の風味や香りを楽しむことはできません。当然、買い付けの段階で“欠点豆”の混入が極めて少ない最高品質のコーヒー豆を仕入れますが、100%混入を避けることは難しいため、手作業で除去していきます。コーヒー豆以外の材料も、他店ではあまり使われていないような高級な材料を使用していますし、コーヒー豆を発送する際のパッケージにもこだわっています。今後はパッケージデザインにもこだわっていけたらと思っています。」
コーヒー豆から発生する炭酸ガスを適度に排出できることに加え、防湿性や遮光性の高い特殊なパッケージを採用することで、コーヒー豆の酸化を最小限に抑え、鮮度を保った状態でお届けできるのだという。
「とにかく質の良いものをお客様に提供したい」というお父様の思いを受け継ぎ、さらにブラッシュアップさせて、今のスタイルがあるのだと話してくれた。


③一宮市に「美味しいコーヒー文化」を
「茶房あずまや」では、お客様に美味しいコーヒーの淹れ方を知っていただいたり、コーヒーの楽しさや奥深さを感じていただくため、ハンドドリップやサイフォン講座、カッピングの体験をはじめとしたイベント・セミナーを直営店で実施している。(※イベント・セミナーの詳細情報は、公式HPにてご確認ください)
これは、今や全国的に知られている一宮市のモーニング文化の裏で忘れられがちな「コーヒーの味」をもう一度見直し、地域全体で「美味しいコーヒー文化」を根付かせたいという思いからだ。
「最近は、モーニング文化に特化しすぎてコーヒーは二の次、三の次になってしまっていると感じたんです。そこで、競合するのではなく、ライバル店やこれから開業しようとしている人たちに僕が持っている知識や経験を共有することで、『一宮市=美味しいコーヒーが飲める場所』として広められたらと考えました。」
モーニング文化が根付き、老舗の喫茶店や珈琲店が多く立ち並ぶ一宮市だからこそ、必ずしも良い反応ばかりではなかったそう。資格を取ったことで、時には「偉そう」と見られることもあったが、それを「注目されている証拠」とポジティブに捉え、より良いコーヒー文化を築くためのエネルギーにしたという。
「一宮市のモーニング文化を残していくために、活発に情報交換をしながら共に成長できる関係を築いていきたいですね。流行りのコーヒーショップではなく、味で勝負できる喫茶店が増えることで地域全体の文化の底上げにつながると思っています。」


④“101” に込められた思いと、コーヒーを通じた社会貢献
オンラインストア『COFFEE ROASTERY 101』、松本さんのお父様が営む『珈琲屋101』と、“101”という数字へのこだわりが感じられるが、取材の最後に、この“101”という数字の由来について、お話を聞くことができた。
「人間も動物も、誰しもが生まれてから1歩、2歩、3歩と成長していきますよね。年齢も1歳、2歳、3歳と成長していく中で、例えば何かに挑戦しようとか、次のステップを目指そうと思ったとき、途中でつまずいたり、諦めそうになったり、絶対に出てくると思います。そこで、僕には無理だ、私には向いてない、と諦めてしまうのではなく、『また1から、初心に戻ってやり直そう』という意味があるんです。」
「あと、学校の試験とかってだいたい100点が上限ですよね。例えば何かに挑戦して、それを成し遂げて、よし100点取った!完璧だ!ってなったら自慢しちゃいますよね。でも僕はそうではなくて、『100点を取ったら、次は101点、102点、103点を目指そう』という考えなんです。100点を取っても偉ぶることなく、常に初心を忘れず101点、102点を目指す。途中でつまずいたら1に戻るのもありだよねっていう想いも込めています。」
さらに、“10月1日”が国際的な「コーヒーの日」であることや、「茶房あずまや」の所在地が“10番地1”であるという偶然の繋がりもあり、多くの意味が重なっている大切な数字なのだと話してくれた。
この“101”という数字は、困難に直面した際に初心に立ち返りやり直すことの大切さ、そして、100点をゴールとせず、さらにその先を追求し続ける成長の意志を表現しているのだ。
今後は、店舗運営を支柱にしながら各地のコーヒーイベントやフェスティバル、マルシェなどへの参加を積極的に行っていきたいと考えているほか、松本さんがオープン当初から掲げている「人のためになることをする」という理念のもと、現在行っている介助犬への支援を継続しながら、次なるステップとして、コーヒー豆の購入を通じて、その地域の土壌改良や生活改善に貢献する活動も視野に入れているという。
この取り組みは生産農家への直接的な支援となり、より品質の良いコーヒー豆の育成につながるだけでなく、乾燥地帯で苦しい状況に置かれる生産者たちを支える重要な役割となるだろう。大規模な寄付は難しくとも、小さな一歩を積み重ねることで、社会に貢献する道を模索し続けている。
喧騒から離れ、ゆったりとした時間を過ごすことができる「茶房あずまや」。国際コーヒー鑑定士の資格を持つ松本さんがこだわり抜いた“極上の一杯”を味わいに、ぜひ一度足を運んでみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら

 一宮市
一宮市