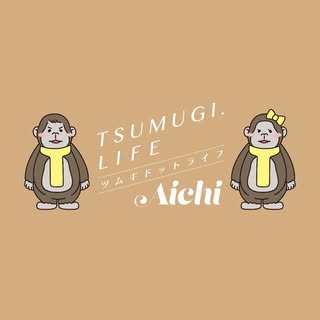農業の新たな可能性に挑戦し続けるごはん屋さん「HACHI米」を訪ねてみた。


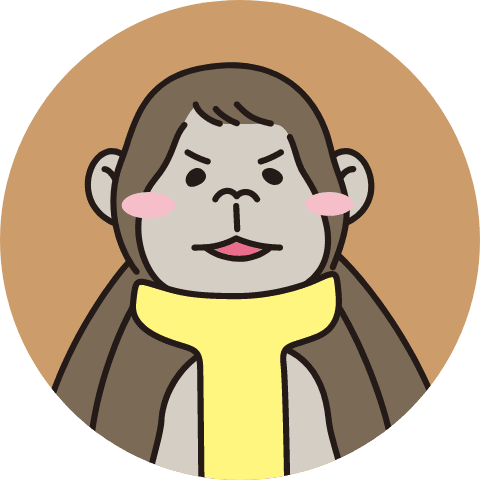
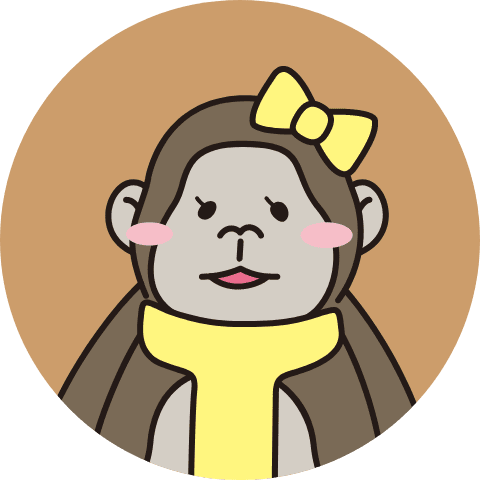
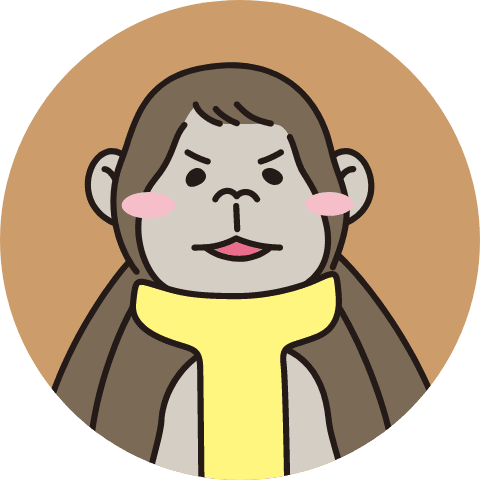
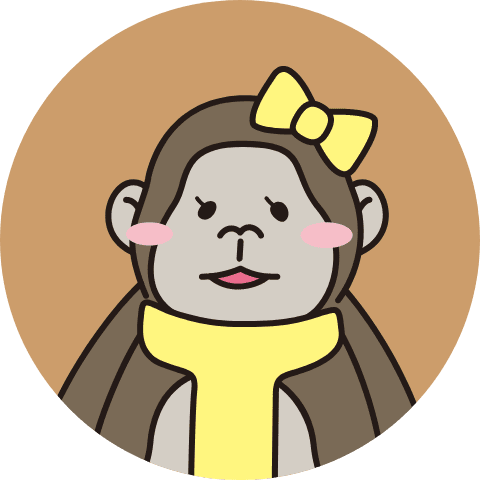
お米農家が、愛知産のお米の魅力を広く伝えるために運営しているご飯屋さんだ。運営母体がお米農家だからこそできる強みや、地元の学生たちとの取り組み、そして将来の展望について、オーナーの八木輝治(やぎ きはる)さんにうかがった。
- 農業法人が飲食店を展開する理由とは
- 農家の強みを活かした、ご飯おかわり自由の定食
- 料理だけではなく「お金の大切さ」も学んでもらう
- 愛知産の安全なご飯でホッとひと息
①農業法人が飲食店を展開する理由とは
「HACHI米(ハチベイ)」は、「変なホテル名古屋伏見駅前」の中にあるご飯屋さん。2022年12月にオープンした。
母体は鍋八農産という、弥富市にある農業法人だ。お米作りを中心に、麦、大豆、デントコーンなどの生産や、田んぼの作業受託、お米の販売などを行っている。
2024年3月には、同じ弥富市内に新たに米粉100%パン・ベーグル・ケーキのお店「EWALU(エワル)」をオープンさせるなど、精力的に活動している。
農業法人が飲食店を出すことにしたきっかけは何だろうか?
「愛知県は、他県と比べて強いブランド米がありません。たとえば新潟なら「コシヒカリ」、北海道なら「ゆめぴりか」や「ななつぼし」がありますよね。」
確かに、宮城県なら「ササニシキ」、秋田県なら「あきたこまち」というような愛知県産米のブランドが、申し訳ないがパッと思い浮かばない。
「でも、愛知県のお米もおいしいんですよ。自分たちで作っているというのもありますが、ブランド米と遜色がありません。鍋八農産は、玄米のままで保管できる低温倉庫を持っています。この倉庫で保存しておけば、品質劣化がほとんど進みません。注文してから精米するので、精米したてのおいしさを届けられます。しかし愛知県内の飲食店でも、お米は他県のブランド米を使っているものが多いんです。」
愛知県産のお米の良さを知ってもらいたい……そこで考えられたのが、「HACHI米」や「EWALU」で実際に食べてもらう機会を増やすことで、おいしさや、安心・安全であると知ってもらう取り組みというわけだ。
おいしさを体感してもらうため、お米は必ずオープン直前に新しいものを炊くようにしている。そしてお客様が何人だったら、どれくらいの水でどれくらいの量を炊くのかというところまで、シビアに計算する徹底ぶりだ。

②農家の強みを活かした、ご飯おかわり自由の定食
「HACHI米」はホテルの中で営業している。なぜ、ホテルだったのだろうか?
「名古屋のお客様にどうやって愛知県産のお米を届けようかと考えていたときに、たまたまホテルの運営会社から声をかけていただいたんです。最初は「朝食でおにぎりを提供するテナントの事業を担っていただけないでしょうか?」という相談でした。」
ホテルの朝食といえば、バイキングをイメージする人も多いかもしれない。しかしコロナ禍以降、状況が変わりつつある。
「今は朝食を、ワンプレートで出すところが増えています。今でもときどきテレビでコロナの報道をしますよね。飲食もやりながらホテルの運営というのはリスクが高く、飲食は別の事業者にお願いするというやり方に変えていくということで、お話をいただきました。次はいつこのようなチャンスが訪れるかわかりませんし、しかも、ありがたいことに一等地ですからね。チャンスと自分たちの想いが一致して、やるしかないだろうという感じでした。」
準備期間は8か月。新規事業を立ち上げるにはかなり短かい。それでも鍋八農産は、この話を受けることを決め、走り出した。
HACHI米の朝食プレートは1,500円。値段だけ見れば、朝食なのに高いと感じる人もいるかもしれない。しかしInstagramの写真を見れば「1,500円でこんなにたくさん食べられるの?」と驚くはずだ。
「このプレートは僕もまかないで食べているのですが、いつも量を少なめにしてもらっているのですが、それでもお腹いっぱいになりますね。」
さらに、ご飯と生卵がおかわり自由なのもとてもうれしいポイントだ。このような価格設定ができるのは、農家ならではの強みだ。
「野菜は、品質としては全然問題ないのに、B級品になってJAに出荷できなかった野菜を直接買い取っています。あと、つながりのある農家の皆さんから、ご厚意でいただけたりするんです。大根が30本入ったかごが10個届いたり、キャベツが10玉入った袋が10袋届いたりするんですよ。」
まさにSDGs。時代の流れに合致しているといえる。そしてもちろん、お米も安く仕入れられる。
「お米は、ほぼ生産原価です。米不足でスーパーにお米がない状態のときでも、おかわり自由です。そしてお米と野菜で仕入れ値を抑えられる分、肉と魚にはこだわって、国産かつ地元のものを使っています。鶏肉は錦爽鶏(きんそうどり)や奥三河の鶏を使っています。豚肉も愛知県産ですし、魚も東海3県で水揚げされたものなんですよ。」
お米と野菜の仕入れを抑えられる分、肉や魚をちょっといいものにできる。お客様も嬉しいし、かなり大きな強みだといえるだろう。

③料理だけではなく「お金の大切さ」も学んでもらう
HACHI米の取り組みで面白いのが、産学連携だ。
名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校と提携し、ランチメニューの開発を行っている。どのような経緯があったのだろうか?
「もともとは調理師の専門学校だったのですが、新たに農業部門を立ち上げたんですね。その理由が、食材の仕入れから提供するところまで、一貫して学ばせたいという学校の想いがあったんですね。」
その背景にあるのは、料理人の離職率の高さだ。
「料理の勉強だけして、数字が全く見えていない人が多いんです。その結果、自分でお店を出しても採算が合わずにやめてしまいます。そこでその学校では、自分たちで野菜を栽培して、どうやって野菜の卸値を決めるか、どういう価格で販売すれば利益が出るのかを学ぶんです。」
料理人として栽培する、卸す、仕入れる、調理する、提供する、お金をいただくという一連の流れを把握する。そのために農業を学ぶというわけだ。
その学びの一環で、学校からHACHI米に相談があったという。
「相談内容は、生徒たちが考えたメニューを販売してほしいというものでした。いくつかのグループに分けて、審査をして、特別賞を獲得したメニューだけで良いから販売してほしいというものだったのです。」
しかし八木さんは、ここで一つの提案をする。
「僕たちも審査をしますが、お客様からの客観的な評価が、このカリキュラムには絶対に必要です。だから全員分やりましょうという話をしたんです。」
そして本当に、生徒たちが考案したメニューを週替わりで提供するようになったのだ。
一見、すべてのグループのメニューを販売するよりも、入賞したグループのメニューだけを販売する方が手間がかからないし、確実だ。しかしこのやり方は、学生たちのためになるだけでなく、HACHI米側にもメリットがあったという。
「週替わりのメニューって、考えるのがけっこう大変なんですよね。仕入れる材料のことや、調理方法や提供方法など全て考えなくてはなりません。それら全てを学生が考えてくれるので、こちらは実現できるように行動するだけなので、手間は大幅に省けます。なので、全員分やりましょうと提案したら、学生や先生たちがすごく感動してくれました。」
八木さんがそんな提案をした背景には、農業への想いがあった。
「農業は、工業などに比べてIT化や自動化などの成長が遅れている分野です。大きな原因は、国の減反政策にあります。社会の授業で習ったと思いますが、米の過剰生産を抑え、米価を維持するために国が米の生産量を調整する制度です。味に関係なく、作付けさえすれば、国からお金がもらえたんですね。」
減反政策は、2018年に廃止された。その結果、たくさんの小さな農家が廃業していったという。
「廃業していった多くは、国からお金がもらえるからと、自分たちで事業展開したり、販売先を開拓したりして来なかった農家でした。原価や減価償却など、お金のことに無関心だったのです。学生さんたちにも、お金の大切さをこの取り組みを通してわかってほしいと考えたのです。」
農業法人として、飲食業者として、お金を意識することの大切さを痛いほど知っている、だからこそ、学生たちにも親身になれるというわけだ。
興味深いのが、審査で1位から3位にも特別賞にも選ばれなかったメニューが、お客様からの一番人気を獲得したことだ。
「そのメニューは、HACHI米のグランドメニューになりました。僕たちは1か月おきに売れたメニュー、売れなかったメニューをしっかりと見ています。決められた売上を超えなかったものはグランドメニューから外しています。でもその学生が考案したメニューは、ずっとグランドメニューから消えていないんですよ。」
この取り組みの結果、学生たちが得られたものはとても大きい。
「名古屋のこのエリアでは、どんなメニューがウケるのか、原価はどれくらいで、販売価格はどれくらいにすればいいのかが見えてきます。そうすることで、学生たちは卒業までに、業界で役立てられる指数をひとつ手に入れられるんです。」
実際にメニューを売る体験を通して、料理だけではない、この社会で生きていくための武器を手に入れられるというわけなのだ。
④愛知産の安全なご飯でホッとひと息
HACHI米のターゲットは、20代から30代の女性だという。なぜだろうか?
「昨今、物価が高騰し、電気代や水道代も上がっています。しかし給料はなかなか上がりません。特に20代や30代の女性にとって、子育ても含めてこの問題が特に重くのしかかっているのです。そんなストレスを抱えた共働きの女性たちが、安心・安全なものを食べてホッとできる場所にしたいと考えています。」
HACHI米には、もともとターゲットとして想定していなかった、40代から50代の男性も多く訪れるという。
HACHI米は、健康を気遣いながら日々頑張るビジネスパーソンにとって、疲れた羽を休めて新たな活力を得られる場所となっているのだ。
最後に、将来の展望についてうかがってみた。
「もっといろいろなホテルにテナントを出したいですね。ホテルを利用する方って、地元の方だけではなく、地方から出張や旅行で来る方が多いのですよ。そして彼ら・彼女らは地場のものを食べたいと考えているんですね。地元・愛知の食べ物を提供できる私達は、そういったニーズとの親和性が高いと考えています。僕もそうなのですが、せっかく違う土地に行ったのであれば、その土地のものを食べたいですからね。」
HACHI米には「名古屋セット」というメニューがある。その名の通り、名古屋の名物である手羽先と天むすを味わえるお得なセットだ。
わざわざ専門店に足を運ばなくても、名古屋らしさを満喫できるのがうれしい。
HACHI米の取り組みは、単なる飲食事業の枠を超えた、地域農業の活性化と食文化の発展を目指す革新的なプロジェクトといえる。
農家の視点と経営者の発想を融合させたアプローチは、地方の農業が直面する課題に対する一つの解決策を示しているといえる。
愛知県産米の魅力を広く伝えるというミッションのもと、HACHI米は今後も新たな挑戦を続けていくだろう。
HACHI米の取り組みは、日本の農業の未来に新たな可能性を開くきっかけとなるかもしれない。

詳しい情報はこちら

 中区
中区