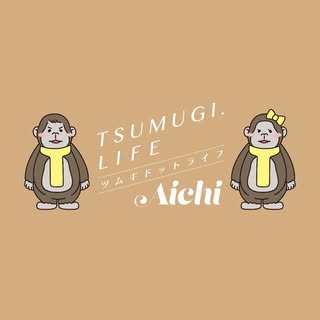温かい郷土の味が息づく「たけうま工房」を訪ねてみた。


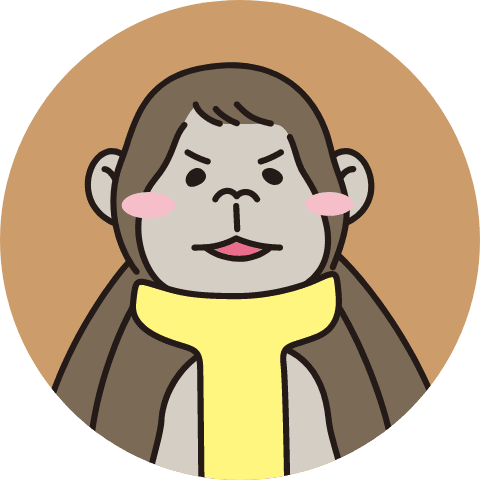
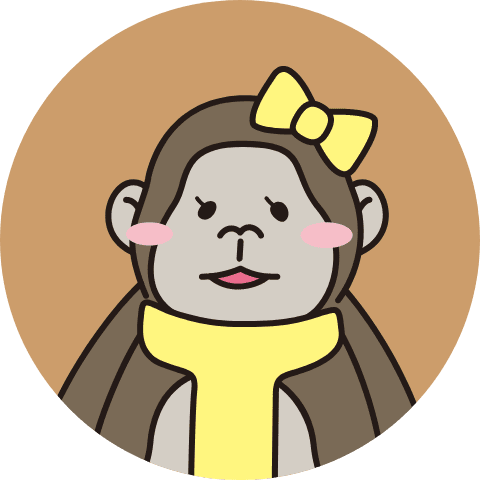
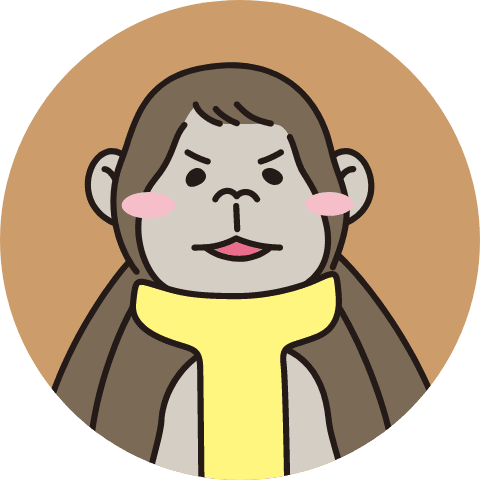
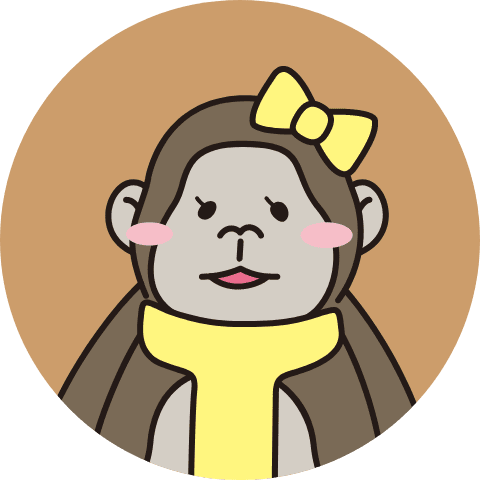
マルシェを中心に、母娘でくるみ五平餅や玄米だんごを販売している。今回は、店主の山田 篤子(やまだ あつこ)さんと、娘の喜多川 由果(きたがわ ゆか)さんにお話をうかがった。
- 「食べたい」から始まった、五平餅への愛
- 「できたて」へのこだわりと「ご縁」が紡ぐ味
- 五平餅の可能性を広げる挑戦と未来への継承
- 感謝の気持ちを忘れず「目の前の人」を大切に
①「食べたい」から始まった、五平餅への愛
県内のマルシェやイベント会場を中心に、くるみ五平餅と玄米だんごを販売する「たけうま工房」。古くから地域に根ざす郷土料理である五平餅は、一口食べれば自然と笑みがこぼれる。
屋号の「たけうま工房」は、篤子さんの名前の漢字「篤」を竹と馬に置き換え、ものづくりが好きなことから、「工房」を組み合わせて名付けられたという。このユニークで遊び心あふれる名前は、二人の人柄とお店の温かい雰囲気をそのまま表している。
五平餅は、岐阜県、愛知県、長野県などの中部地方の山間部で古くから伝わる郷土料理だ。半搗き(はんつき)したうるち米を串に巻き、味噌や醤油ベースのタレをつけて焼くシンプルな食べ物だが、その形やタレ、そして文化は地域によって大きく異なる。
篤子さんは、幼い頃からこの五平餅に親しんできた。篤子さんの地元の五平餅は、タレにくるみやごま、ピーナッツなどを使った甘辛い味付けで、小判型やわらじ型が主流だ。一方、地元から離れた地域で出会った五平餅は、味噌ベースのタレで団子状のものが多い。昔から食べ慣れた五平餅が手に入らないことに気づいた篤子さんは、心の中でこう思った。
“食べたい五平餅が売っていないなら、自分で作ればいい”
そう考えた、篤子さんは五平餅づくりを始める。当時、自転車店を営む息子さんの手伝いをしていた篤子さん。店で定期的に開催されるイベントで、サイクリングを終えた人々に五平餅を振る舞っていた。
「五平餅を振る舞っていたら『こんなに美味しいんだから、商売にしたらいいのに』なんて言われて、嬉しくなってついその気になってしまったんです。」
しかし、商売を始めるには、店舗を構えるなどの費用や労力がかかる。躊躇していた篤子さんに、ある日転機が訪れる。息子さんと関市に訪れた際、立ち寄った材木屋で小さな可愛らしい小屋を見つけた。もういらないからと安く譲り受けたこの小屋が、自転車店の駐車場のデッドスペースにぴったり収まったのだ。
「最初は、『自分が食べたいから』という気持ちで作り始めたんです。でも、ありがたいことにいろんな方からすすめていただいて。かわいい小屋と場所も見つかって、販売もしてみようかなと決心しました。」(篤子さん)
もともと瑞浪市で自然薯料理店を経営していた経験を持つ二人。飲食業のノウハウは身についていた。美味しい五平餅を自分で作りたいという純粋な気持ちと、偶然にも訪れた小屋との出会いが重なり、たけうま工房は産声を上げた。

②「できたて」へのこだわりと「ご縁」が紡ぐ味
たけうま工房の強みは、何といってもその「味」だ。美味しい五平餅を届けたいという情熱は、徹底した「できたて」へのこだわりへとつながっている。注文を受けてから一つひとつ丁寧に焼き上げるため、作り置きはしない。
「時間が経つとタレの状態が変わってしまうので、できるだけ温かいうちに食べてほしいです。」(篤子さん)
二度焼きすることで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上がる。一口頬張れば、タレの香りと米の甘みが口いっぱいに広がる。その絶妙な加減は、長年の経験がなせる技だ。五平餅のタレには、くるみをたっぷりと使用。くるみとごまの油分がしっかりとタレに溶け込み、深いコクとまろやかさを生み出す。
くるみ五平餅と並ぶもう一つの看板商品が、無農薬の米農家の玄米を使用した玄米だんごだ。定番の「みたらし」と「焼き醤油」のタレは、手絞りの醤油や手作り味噌など、地元の厳選された食材を使用している。
「どの醤油を使おうかと考えていたとき、醤油作りに誘われたんです。ご縁があって、その醤油を使わせてもらっています。」(篤子さん)
玄米だんごのタレは、醤油は二度付けして香ばしさを出し、みたらしは焦がすなど、種類によって焼き方を変えているという。こうした手間ひまを惜しまない姿勢が、多くのファンを引きつける理由だろう。
たけうま工房の歴史はさまざまな「ご縁」によって紡がれてきた。自転車店での五平餅の振る舞いから始まり、偶然見つけた小屋、周囲からの声かけ、そして手絞りの醤油との出会い。美味しい五平餅を作りたいという純粋な思いに、多くの人や出来事との「ご縁」が重なり、今のたけうま工房へと自然な形で発展していったのだ。


③五平餅の可能性を広げる挑戦と未来への継承
たけうま工房は、伝統の味を守りながらも、新たな魅力を生み出す挑戦を続けている。その一つが、五平餅の生地に野菜を練り込むというものだ。イベントで出会った農家から直接仕入れた新鮮な野菜を使うことで、新たな魅力が生まれた。
「生地に野菜を練り込むというのは他にないと思います。もともと五平餅は栄養価が高い食べ物ですが、旬の野菜を加えることで、さらに栄養をプラスできます。小腹が空いたときに、手軽に栄養を摂れる携帯食のように楽しんでもらえたら嬉しいです。」(由果さん)
トウモロコシ、里芋、レンコン、菊芋など、季節によって練り込む野菜はさまざまだ。特にトウモロコシを練り込んだ五平餅は、焼くことで甘みが引き出され、プチプチとした食感が楽しめる。子どもから大人まで、幅広い層に大好評だという。
「イベントなどに出店すると、本当に美味しいものを作る人たちにたくさん出会います。みなさん、一つひとつ丁寧に作られていて、その人のこだわりや物語がある。そんな人たちとの出会いが本当に楽しいんです。それに、五平餅を美味しそうに食べているお客様の姿を見ると本当に嬉しくなります。」(由果さん)
現在、たけうま工房は篤子さんから由果さんに引き継ぐ準備を進めている。長年培ってきた母の味と技術は、娘へと引き継がれ、これからも変わらない味を提供し続けていくのだ。
「母の美味しい五平餅と玄米だんごを、守っていきたいです。これからも変わる事なく皆さんに美味しいと言ってもらえるように頑張りたいです。」(由果さん)
互いを思いやり、協力し合いながら、たけうま工房は次世代へと歩みを進めている。


④感謝の気持ちを忘れず「目の前の人」を大切に
たけうま工房が大切にしているのは、「誰もが気軽に味わえる、素朴なおいしさ」だ。おやつにも、小腹が空いたときにも、日々の生活に寄り添う存在でありたいという。そのため、価格もできるだけ抑え、誰もが手に取りやすいよう配慮している。
「子どもからお年寄りまで、みなさんに気軽に楽しんでほしいんです。メインでなくても、小腹を満たしたいときなどに、気軽に手に取ってもらえたら嬉しいです。」(由果さん)
「当時は小銭を握りしめた子どもたちが笑顔で買いに来てくれるのが嬉しくて、今まで頑張ってこれました。」(篤子さん)
と、開業当時を振り返る。
今後の展望について、二人は「何か新しいことを広げるというよりは、継続していくことに力を入れたい」と語る。イベント出店を続けながら、いつかまた自然薯料理も提供したいという夢も抱いている。
「ただ、今はイベントへの出店を無事に終えることと、『美味しかった』とまた買いに来てくれることが一番嬉しいので、目の前の一本を丁寧に作ることに集中したいです。」(由果さん)
二人が何よりも大切にしているのが、「ご縁」と「目の前の人を大切にする」ことだ。今回の取材中も、その思いが随所から伝わってきた。
「どれだけ売上があったか、何本売れたかということよりも、あの時のお客様にちゃんと対応できたかな、満足してもらえたかな、というのを大切にしています。とにかく目の前の、一人ひとりのお客様の為に頑張りたいです。」(由果さん)
美味しいくるみ五平餅と玄米だんごを通じて、人と人との縁を紡いでいく『たけうま工房』。二人の温かい人柄と丁寧な仕事ぶりは、多くの人々の心を掴んで離さない。
郷土の味が持つ温かさ、そして手作りのぬくもりをぜひ一度味わってみてほしい。マルシェやイベントで見かけた際は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら