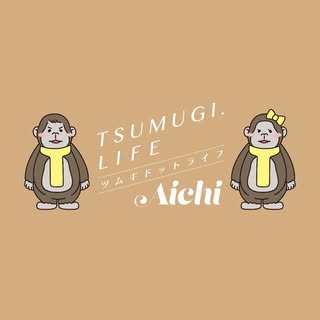オープンキッチンのフレンチ×鉄板焼きで新境地を拓く「HONJIN」を訪ねてみた。


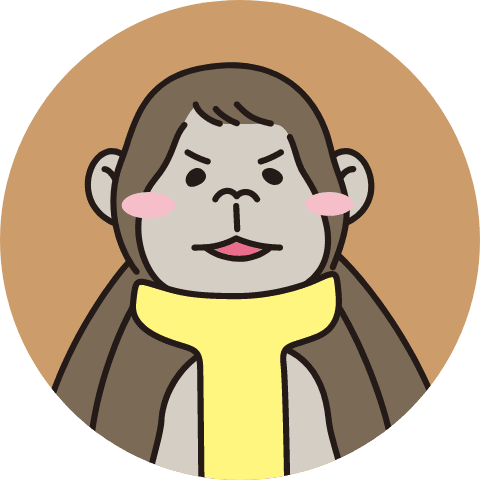
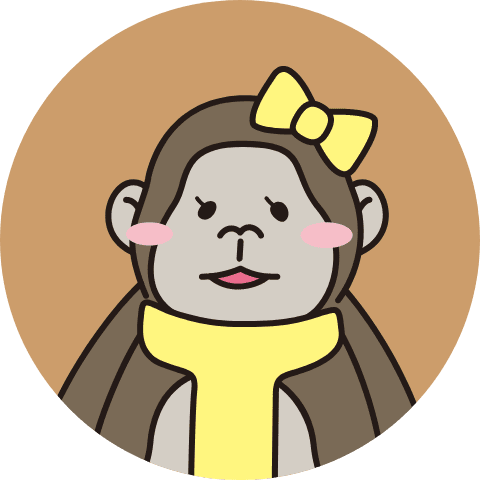
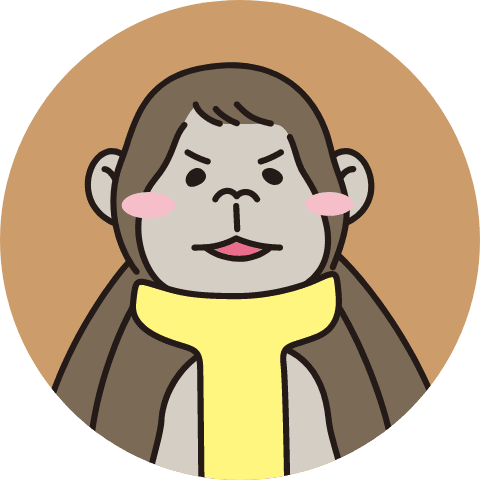
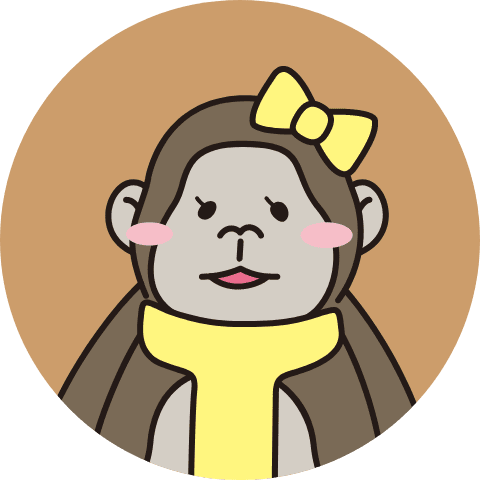
オープンキッチンでフレンチを楽しめるスタイルで注目を集めているレストランだ。フレンチの修行時代のエピソードや、大切にしていることなどを、オーナーシェフである田島 裕大(たじま ゆうだい)さんにうかがった。
- 鉄板焼きにフレンチの風を取り入れてリニューアル
- 19歳で渡仏し、三つ星レストランに就職
- プレッシャーと戦いながら技術を磨く
- 地元の食材を使った五感で味わうフレンチ
- つながりを大切にするレストラン
①鉄板焼きにフレンチの風を取り入れてリニューアル
HONJINは、一宮市にある27年間続く鉄板焼きのお店だ。2021年に「鉄板焼き」と「フレンチ」の2つのシーンを楽しむことができるレストランへと生まれ変わった。
その歴史は、田島さんのおじいさまの代までさかのぼる。
「もともとは、祖父が喫茶店を経営していました。その当時から、HONJINという屋号を使っています。その後、父親が鉄板焼きのお店「ステーキ&シーフード HONJIN」にしたんです。」
本陣は、「総大将がいる場所」以外に「大名や旗本などの身分の高い人が小休止する建物」という意味がある。お客様がゆっくりできる場所をイメージとして名づけられ、それを田島さんが引き継いでいるのだ。
鉄板焼きはジャンルの垣根がなく、メニューによって、和風になったり中華風になったり洋風になったりと自由度が高い。しかし田島さんは、お父様と同じ鉄板焼きではなく、あえてフレンチというひとつのジャンルを極める道を選んだ。
「鉄板焼きも魅力的なのですが、僕はもっと前菜など美しい料理をつくりたいと思いました。美しい料理とは何だろうと考えたときに、浮かんだのがフレンチでした。自分がこの道で勉強すれば、HONJINがもっとよくなると考えたんです。」

②19歳で渡仏し、三つ星レストランに就職
田島さんは高校を卒業後、辻調理師専門学校に進学した。その後、19歳で同校のフランス校へ進学し、フレンチを学んでいる。
「フランス校では、最初の5か月で料理や接客、フランス語を学び、それが終わったあとは現地の二つ星レストランで研修を受けました。」
10か月フランスで学んだあとは、東京に戻り「ジョエル・ロブション」に就職する。「ミシュランガイド東京2024」で、17年連続三つ星に選ばれているレストランだ。
「厳しいところに就職して学びたいと考えました。自分を取り巻く環境を落とすのは簡単ですが、上げるのは難しいですからね。現地で出会った日本人の方に相談したら、「良いところを紹介してあげる」と言われて、それが三つ星レストランだったんです。」
就職のタイミングも良かったと、田島さんは語る。
「実は、すでに新入社員の募集は終わっていました。しかし僕は紹介で入社したので、新卒なのに中途社員のような扱いだったんです。ですから新入社員の人たちよりも2週間早く入社して、早く仕事を覚えられました。」
そして田島さんは、入社半年で肉を焼くという重要なポジションを任せられることになった。
③プレッシャーと戦いながら技術を磨く
ほぼ新卒なのに三つ星レストランに入社半年で、お肉のポジションを任される……飲食業界に詳しくない人でも、すごいことだというのがわかる。
「ステーキ屋の息子だからお肉も焼けるでしょという感じでシェフから指名されたんですが、そんなに簡単に焼けるわけがないんですよね。入って半年の新人が三つ星レストランでお肉を任される、肉を焼くポジションに行きたい先輩も多く、正直プレッシャーでしかなかったですね。」
まだ遊びたい年頃の20代前半の若者にとって、さぞかし大変な日々だったと推測できるが、やめたいと思ったことはなかったのだろうか?
「ないですね。自分がうまくできなくて、みんなに迷惑をかけているという思いでいっぱいでした。また、自分がやっていいのだろうかという、申し訳ない気持ちもありました。でもシェフから指名されたからには、必死にやるしかない。やめたいと考える余裕はありませんでした。」
4年後、当時のシェフが独立し、田島さんも一緒にそのシェフについていくことに。そこでも4年間にわたってお肉を担当した田島さん。
実務経験をしっかり積んだ上でHONJINをリニューアル……と思いきや、驚くべきことに田島さんは再度、フランスに渡航して勉強している。なぜだろうか?
「8年間、同じシェフの元でしかフレンチをつくっていませんでした。一緒に仕事をしていたシェフは完璧すぎて、同じようにやろうとしても、おそらく不可能だと感じました。ですから、いろいろなシェフのやり方を見て学びたいと考えたんです。」
フレンチに対する、田島さんのあくなき探求心と努力が、HONJINの土台となっているのだ。

④地元の食材を使った五感で味わうフレンチ
HONJINではオープンキッチンの他に、どのようなこだわりがあるのだろうか?
「素材を重視しており、地元の食材を使うことにこだわっています。食材はほぼ愛知県産ですね。あと僕は、出身が岐阜の羽島なんです。母方の祖父母が山菜取りとか釣りが好きで、よく泊まりに行っていました。イナゴを捕まえたりとかもしていましたね。岐阜も僕のルーツなので、器は多治見や土岐の美濃焼の器を使っています。肉を切るための包丁も、関市のものなのですよ。」
関市は日本一の刃物の町。田島さんのようなプロが選ぶのも納得だ。
「この包丁をお客様にお渡しして、メインのお肉を切っていただくこともあります。このような食体験を提供できるのも、オープンキッチンならではですね。」
美しいフレンチを目で見て、肉の焼ける音や香りを感じ、包丁を使って体験して、舌で味わう。お客様が五感をフル稼働させて楽しめる。
オープンキッチンの強みを最大限に生かしているのがHONJINなのだ。
リニューアルにあたり、フレンチ一本にしようとは考えなかったのだろうか?
「鉄板焼きのHONJINには30年近い歴史があり、そこに根付いているものがあります。それを大事にしようと思いました。鉄板焼きとフレンチは、客単価も客層も異なります。鉄板焼きは昔ながらのスタイルで、みんなでワイワイしているイメージです。一方で、フレンチは空間そのものを楽しむものなんです。」
口コミの中には「以前の方が良かった」というものもある。田島さんは、そのような意見に対しても、丁寧に返信している。
「一宮の地元の皆さんのために、鉄板焼きは残しています。ただ、父がやってきたことと、僕がやりたいことは異なります。食文化を変えたいという僕の想いを、お客様にもしっかり伝えるようにしています。」
そしてHONJINは、東京・北海道・大阪・福岡など、全国から舌の肥えたグルメが訪れる場所となった。フレンチということで、年齢層が高いかと思いきや、意外に若い人も多く訪れるという。
「最初は緊張したけど、シェフの方が話してくれて打ち解けられましたという若い方からの口コミもありますね。」
フレンチといえばテーブルマナーが厳しいイメージが強いが、HONJINはお箸もOKなのがありがたい。
全国からファンが訪れるHONJINだが、今後は行政と連携するなど、もっと地元にも力を入れていきたいと考えているそうだ。

⑤つながりを大切にするレストラン
料理の修行というと、最初のうちは皿洗いなどしかさせてもらえないなど厳しいイメージがある。少し前にも、寿司職人の修行に10年かかるという話がネットで物議を醸した。
しかしHONJINの場合は、新卒の若手にも積極的に肉を焼かせたりしているという。
「若手にいろいろ経験をしてほしいと考えています。経験が自信につながりますし、絶対プラスになりますからね。2番手のスタッフは、コース料理の中の一品をつくってもらっています。僕の料理をつくってもらうだけだと、せっかくオープンキッチンでお客様が食べて喜んでいるのを見ても「これは自分の料理じゃないから」となってしまいます。1品任せることによって、自分の料理を食べたときのお客様の反応を直に見られるんです。僕は若いころ、お客様の笑顔を見ながら料理をつくりたいと思っていました。決して自分の意見を押し付けるわけではないですが、本人が乗り気ならどんどんつくってもらいます。」
自分がつくった料理でお客様の笑顔が見られたら、とてもうれしいし、良い経験になる。オープンキッチンの特性が、教育の面でも存分に生かされているというわけだ。
最後に、田島さんが大切にしていることについてうかがった。
「HONJINのコンセプトは「つながり」です。生産者の方を大切にし、実際に畑や農場に自分で足を運んでいます。オープンキッチンにしているのは、生産者の方の想いをきちんと伝えられるからというのもあるんです。これからもつながりを大切にしていきたいですね。」
正直に言って、取材の前はフレンチのシェフに対し、どこか気難しそうなイメージがあった。しかし田島さんは気さくでとても話しやすい。
生産者の方とのつながり、お客様とのつながり、そしてスタッフとのつながり。HONJINにはたくさんのあたたかなつながりがあるが、それは田島さんの人柄の賜物でもあるのだろう。
田島さんが持つ料理への情熱と技術、そしてつながりを大切にする姿勢は、HONJINを唯一無二のフレンチ&鉄板焼きのお店として確立させている。フレンチが大好きな方はもちろん、普段なかなか食べる機会がないという方も、ぜひHONJINで新しい食を体験してみてはいかがだろうか。

詳しい情報はこちら

 一宮市
一宮市